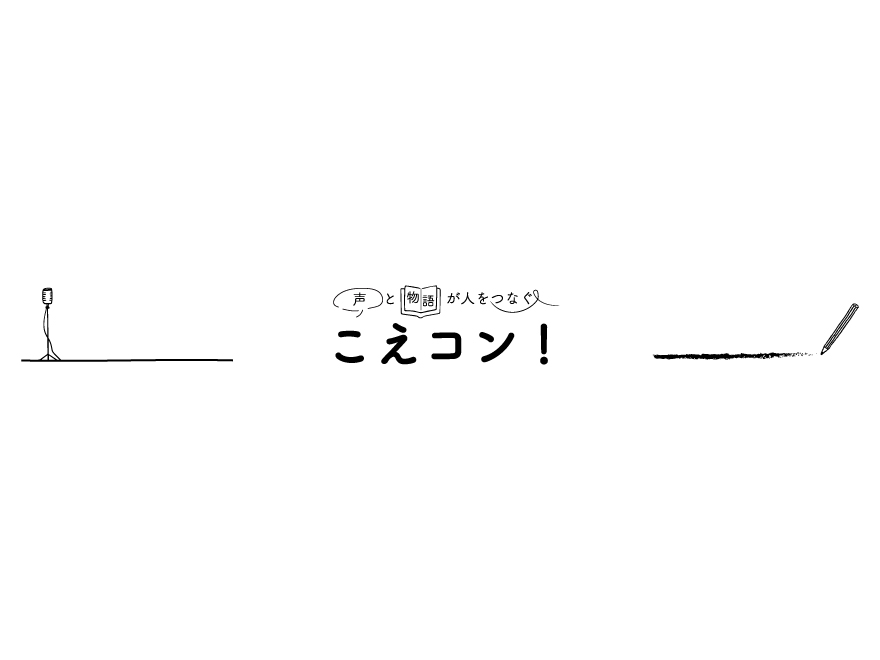第1回「しなコン!」ショート部門受賞作品
「ひび割れた指にささくれがたつー」
作家・落合は自宅で書き物に耽っていた。そこへ編集の秋庭が退職の挨拶に訪れ、書きかけの文章を覗こうとして咎められる。二人は手土産を食べながら話す。秋庭は退職理由を、実家の仕事を手伝う為だと言う。
素直じゃない落合は、好物にも退職にもそっけない反応をするが、ファンでもある秋庭は言葉の意味を理解してると楽しげに笑う。食事を終えた頃、秋庭が落合の指にささくれを見つけ……
タイトル
ささくれ
作者
ものかき
作者サイト

ジャンル
ヒューマンドラマ/ラブストーリー
上演時間
約10~20分
男女比
女1:不問1
落合
おちあい。不問、作家。
秋庭
あきば。女、編集。(性別変更可)
――ページを捲る音
落合
(M)ひび割れた指に、ささくれがたつ。
落合
ただそこにあるだけなら、目障りで済むというのに。それは何をするにも引っ掛かり、私の心を苛立たす。
落合
いっそのこと引きちぎってしまいたい。
落合
しかしそれは、痛みを伴うだろう。
落合
そう思うと踏ん切りつかず、私は今日も、指先の厄介を恨んでいる。
落合
こんなに心乱されていることを、きっと君は知らないだろう。
――ページを捲る
(場面転換)
――原稿用紙にペンが走る音
――扉が開く
秋庭
「先生、そろそろ休憩にしませんか?」
落合
「……」
秋庭
「先生?聞こえてますかー!」
落合
「……」
秋庭
「先生の好きなバッテラ、買ってきましたよー!」
落合
「……」
秋庭
「… 頭でっかちこけし」
落合
「聞こえてるぞ」
秋庭
「聞こえてるなら返事して下さい!」
落合
「悪口のチョイスにこけしはどうなんだ?」
秋庭
「赤べこの方が良かったですかね」
落合
「だからなんで人形なんだよ。もっと他にないのか」
――手を止めて振り向く
秋庭
「常吉のバッテラ、買ってきましたよ」
落合
「腹は減ってない」
秋庭
「そんな事言ってると、また食事を忘れるんですから!体調不良の作家なんてもう流行らないですよ?いっぱい食べて、しっかり寝て、たくさんいい話をかかないと」
落合
「君も大概しつこいな」
秋庭
「分かってもらうまで何度でも言い続けますよ」
落合
「わかった、食べればいいんだろう、食べれば」
秋庭
「はい。私もいただきます」
秋庭
「ん~美味しい」
落合
「本当は君が食べたいだけなんじゃないのか?」
秋庭
「失礼な。ちゃんと差し入れですよ。先生の好物でしょう?」
落合
「そんなこと言ったか?」
秋庭
「言いましたよ、3年前に。新刊の受賞パーティーの帰り、先生がまだ飲み足りないって言って入った寿司屋で。まあ先生、あの時べろべろに酔ってましたけど」
落合
「そんな昔のことをよく覚えてるな」
秋庭
「当然じゃないですか」
落合
「酒で鈍った舌に、酢飯の酸味が丁度良かっただけだろう」
秋庭
「じゃあ、好きじゃないんですか?」
落合
「……どちらかと言えば、嫌いじゃない」
秋庭
「ふふ。つまり『大好き』って事ですね」
落合
「は?」
秋庭
「先生が素直じゃないことは、よく知ってますから」
落合
「……」
――ページをめくる音
落合
(M)風が轟々と窓を叩く。
落合
私はその音を、布団の中で聞いていた。
落合
ようやくちぎりとった思いが、またにょきりと頭をもたげるのに辟易(へきえき)としていた。何度も繰り返すささくれと同じ、むけばむくほど深くなる。
落合
いっそ指ごと切り落とせば、楽になるだろうか。落ちた薬指を見たらこの心は落ち着くだろうか。そしてその時、私はこう言うのだ。
落合
『ザマァミロ、勝手に生えてくるからだ』
――ページを捲る
秋庭
「それで先生、何を書いてたんですか?」
落合
「あ?」
秋庭
「今月分の原稿はもう頂きましたし、何か新しい話を思いついたとか?」
――原稿を覗こうとする頭を叩く
秋庭
「ぁいた」
落合
「勝手に見るな。ただの悪口だよ」
秋庭
「悪口?」
落合
「ああ。何度も家に来る集金や、頻繁に顔を出す厄介な編集者とかのね」
秋庭
「集金は回ってきて当然ですけど、まめに顔を見せるなんて、その編集の方はとても先生の事が好きなんですね。大事にされてますね先生、自慢に思った方がいいですよ?」
落合
「来世があったらそうするよ」
秋庭
「今からでもまだ遅くないですよ!」
落合
「遅いだろ、もう辞めるんだから」
秋庭
「あ、 …ふふ。そうですね」
秋庭
「今日はその挨拶で来たんでした」
落合
「……」
秋庭
「先生、今まで本当にありがとうございました。先生の作品づくりに携わらせて頂いたことは、私の人生の宝です」
落合
「いつ行くんだ?」
秋庭
「今月中には」
落合
「実家に帰るんだったか」
秋庭
「はい。仕事を手伝うことになって」
落合
「ほぉ」
秋庭
「うち、農家なんです。今はまだ二人とも元気なんですけどね。結構前から早く帰ってこいって言われてて、何とか誤魔化してたんですけど、まぁいつまでもそうは言ってられないし、この辺が引き際かなと」
落合
「…そうか」
秋庭
「全然帰る実感わかないんですよ。ずっとこっちに住んでたから引越しなんて久しぶりだし」
落合
「君は私でも呆れるほどの読書マニアだ。準備といいながら、片すはずの本に齧り付いてるんじゃないのか?」
秋庭
「そうなんですよ!何度読んでも先生の本が面白いせいで、つい夢中になってしまって」
落合
「ふ、君らしい」
秋庭
「ふふふ」
落合
「ま、体に気をつけてな」
秋庭
「ありがとうございます、先生も」
落合
「ああ」
秋庭
「私がいなくても、ちゃんと食べなきゃダメですよ?休憩も。後任の子にはまめに様子を見る様に言っておきますが、」
落合
「心配しなくても大丈夫だ。それより、自分の心配をしなさい。急に畑仕事なんて出来るのか?」
秋庭
「あはは、確かに。…そうですね」
――ページをめくる音
落合
(M)指先に、じわりと血が浮いていた。
落合
ついにあのささくれがいなくなった。
落合
今度こそ二度と生えてくる事はないだろう。
落合
これで服に袖を通す時も、横になって布団を手繰り寄せる時も、煩わしい思いをせずに済む。
落合
そう思うと安心する。
落合
しかし同時に、私は絶望した。
落合
きっと私はいつか、あんなに小さな君がそこにいた事も、君がどんなに不愉快だったかも、忘れてしまうのだ。
落合
それがこんなにも、寂しい。
――ページをめくる音
秋庭
「はー、ご馳走様でした」
落合
「まあまあだったな」
秋庭
「ふふ、最後まで素直じゃないですね」
――ふと何かに気づく
秋庭
「あれ、先生、指」
落合
「?」
秋庭
「ささくれ、出来てますよ」
落合
「…ああ、本当だ」
秋庭
「最近乾燥してますからね」
秋庭
「放っておくと気になるから、切っちゃった方がいいですよ」
落合
「…そうだな…」
落合
「君、とってくれ」
秋庭
「え?」
落合
「引っ張れば直ぐに取れるだろう」
秋庭
「ええ、でも裂けちゃうかもしれないし、痛いですよ?ちゃんと爪切りで切った方が」
落合
「うちにそんなものない」
秋庭
「普段どうやって爪切ってるんですか…」
落合
「君がやってくれ」
秋庭
「んー。分かりました、やってみます」
――渋々手を包む
秋庭
「痛かったら言ってくださいね」
落合
「ああ…」
秋庭
「いきますよ」
――ぶつり、とささくれを引き抜く
落合
「つ、」
秋庭
「ああ、やっぱりちょっと血が出ちゃいましたね。ごめんなさい、消毒しないと」
落合
「洗っておけば大丈夫だ、直ぐに治る」
――引っ込めようとした手を握る
秋庭
「ダメです、 小さい傷って意外と怖いんですよ?何度も繰り返したり、ばい菌が入って膿む事もあるんですから」
落合
「……ならいっそ、治らなければいい」
秋庭
「え?」
落合
「なんでもない」
――ページをめくる音
秋庭
「じゃあ私いきますね」
落合
「ああ、見送りに行けなくて悪いな」
秋庭
「先生が出不精なのは、よく知ってますから」
落合
「放っておけ」
秋庭
「向こうについたら、手紙を送りますね。写真を添えて。電車もろくに通ってない田舎だけど、大きな銀杏(いちょう)の木があって、とても綺麗なんですよ。見たら、先生も来たくなっちゃうかも」
落合
「…銀杏(ぎんなん)か」
秋庭
「ええ!日本酒のあてに最高です」
落合
「悪くないな」
秋庭
「ふふ。でしょう?他にも美味しいものが沢山」
落合
「あまり食べ過ぎないように」
秋庭
「気をつけます、先生は沢山食べてくださいね」
落合
「…ああ。せいぜい、いっぱい食べて、しっかり寝て、たくさんいい話をかくよ」
秋庭
「私が言った事、ちゃんと覚えてたんですね」
落合
「君が会う度にしつこく言ってたからな」
秋庭
「何度無視されても、繰り返したかいがありました」
落合
「…」
秋庭
「…先生、最後に一つお願いが」
落合
「聞くだけ聞いてやる」
秋庭
「さっき書いてたの、読ませてくれませんか」
落合
「…悪口だと言ったろ。人に見せるようなものじゃない」
秋庭
「良いじゃないですか。誰にも言わないし、私宛の悪口でも構いません。餞別だと思って」
落合
「気が向いたらな」
秋庭
「…ふふ、分かりました」
秋庭
「それじゃあ、行きますね」
落合
「ああ、じゃあな。秋庭君」
秋庭
「…はい、さようなら。落合さん」
――扉が閉まり、家を出ていく
――ぱらぱらとページを捲る音
落合
(M)ささくれは、いなくなっても私を病ませた。
落合
私は傷が治りかける度、何度も抉ってそれを深くする。
落合
ぱっくり割れた指先を見ると、安心するのだ。
落合
まだ傷は癒えてない、君はここにいる。
落合
いつから私は、鬱陶しいと思っていた筈の物に縋っていたのか。傷を毟るのが怖くなったとき?ささくれに気づいた時?…あるいは、その前からか。
落合
きっと君は、清々しただろう。これで偏屈な私から解放されて、どこへでも行ける。私の事など忘れて。
落合
……もしも、もしまた、ささくれと会えたら、私はそれを疎ましく思うだろうか。あるいは次こそ、大事に出来るだろうか。
落合
今はただ、指先から溢れた血が、布団に落ちていくのを眺めている。
――ぱたんと本を閉じる
(場面転換)
――ガタンゴトンと電車の音
秋庭
「引越しギリギリにポストに入れるなんて、意地悪だな。でも先生の『気が向いたら』は、読ませてやるって意味ですもんね。これが悪口?…ああ、悔しいな。先生の言葉は、誰よりも理解してる気でいたのに…。敵わないなぁ、本当に。…ああ、そうだ。向こうについたら直ぐ送れるように、先生に手紙をかいておこう」
――手紙にペンを走らせる
秋庭
(M)まるで体の一部のように、貴方の近くにいて、どれだけ貴方を思っていても、少しも私を見ようとしない。
秋庭
それならいっそ、憎まれてもいい。
秋庭
目障りになれば貴方は私に気づくでしょう。
秋庭
出来ることならそのままずっと、貴方の視界の中にいたい。だけどそれが叶わないなら…。
秋庭
せめて最後に、その指先に噛み付くように、貴方の一部も千切れて欲しい。
秋庭
「…あなたはささくれの気持ちなんて考えないのだろうけど、私にできる仕返しは、こんな些細な物なのです。…先生」
――ガタンゴトンと電車の音が遠のいていく
(終わり)